
土埃が気になった道路 |
チタからネルチンスクまでは未舗装の道路が約300km続き、車での所要時間は片道およそ5時間である。夏場の道路では対向車とすれ違う度にものすごい土埃が舞い上がり、シベリアとはいえ、炎天下では+35度前後になるのに車内にクーラーが無いのは大変だった。
運転手はがっしりとした体格のブリヤート人だった。車は韓国製。
|
 |

牛の大群が道路を横切る
|
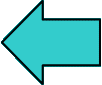 途中の風景は白樺林と牧草地。車道を牛の大群が横断している時もあった。 途中の風景は白樺林と牧草地。車道を牛の大群が横断している時もあった。
途中にあった小屋のようなカフェ。ここには電話があるようだった。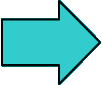
|

街道にあった小さなカフェー
|
ネルチンスクの概要
ネルチンスク(Нерчинск)はチタ州ネルチンスク地区の中心で1658年に設立された。モスクワとの時差は6時間である。
地理的位置 (北緯52度04分、東経116度35分)
ザバイカル地域(バイカル湖より東側地域)の東南、ネルチャ川とシルカ川の合流点から7km離れたネルチャ川の左岸(船着き場がある)に位置している。チタからは東へ305kmの距離である。ネルチンスクから85kmのところに鉱泉療養地区のコルトモイコン(Koltomoikon)がある。
歴史
この町ができたのは約350年前。
初期の町の様子はどうだったのか、開拓者たちが残した記録を参照してみる。
1653年秋、多くの砦や町の建設で名をはせていた100人長のピョートル・ベケトフは、『イルゲニ湖畔とシルカ川沿いの最適な場所に二つの砦を建設せよ。』というロシア皇帝の命を受けてダウリヤ地方にやってきた。
注1.(ダウリヤ(ダウリヤ地方)とはザバイカル地域とアムール流域の西側地域一帯を示す言葉としてロシア人が17世紀頃まで用いていた。「バイカル・ダウリヤ」とはザバイカル地域南方のヤブロノヴォ山脈までの地域であり、「ネルチンスク・ダウリヤ」とはヤブロノヴォ山脈の東側地域でり、「セレンガ・ダウリヤ」とは最も南側の地域を示していた。)
注2.(ヤブロノヴォ山脈はロシア・ザバイカル地域、チタ州にあり、その長さは約650km、最も高い地点で標高1678m)
この二つの砦の一つがネルチンスクだった。イルゲニ湖畔での砦の建設を一段落させた後で、ベケトフは建設隊の一部とともにシルカ川へ向かった。コサックたちはインゴダ川の川岸で筏を組み、目的地へ向かったが、10露里以上は進めなかった。晩秋の寒さが川面を凍結させており、ベケトフは川岸に越冬用施設、弾薬庫、三つの小屋を建設する事にし、50人長のイワン・コテリニコフを隊長とする数名のコサック兵を越冬させた。
また、10人の別働隊をネルチャ川の河口へ向かわせ、自分はイルゲニ砦へ戻った。これが11月の事であったが、1月20日には十人長のマクシム・ウラゾフから「ネルチャ川とシルカ川の合流点のシルカ川右岸に砦を築くに都合がよく、漁労、農耕に適した場所を見つけ、小さな砦を築いた」との連絡が入った。しかし柵で囲まれ、強化された越冬地は長くは存在しなかった。
(この場所には後にモナスティルスコエ村ができ、現在はカリーニノ村となっている。)
1658年、アムール流域に軍管区を設立するために、それまでエニセイスク軍管区に務めていたアファナシー・パシコフがシルカにやって来て、ネルチャ川の中州に新しい砦が建てられた。町の正式な設立はこの年の春であるが、ネルチンスク250周年(1903年)、350周年(2003年)では最初の砦を築いた1653年を基準にしているようだった。町の名はネルチャ川の畔に所在することからネルチンスクと命名された。
1689年、この地で露清の国境を定めたネルチンスク条約が締結された。ネルチンスクは市に昇格した。(参考: この年、ロシアではピョートル大帝が単独即位し、日本では松尾芭蕉が「奥の細道」の旅に出た。)
1812年、たび重なる洪水により、ネルチンスクは高い場所(現在のネルチンスク市があるサジコフ・ヤル盆地)へ移った。(参考:この年、ロシアでは「ボロジノの戦い」があり、ナポレオン軍を撃破)
19世紀末にネルチンスクでは毛皮(狐、リス、毛長イタチ、オオカミ)、手工業製品、クングル靴(クングルはペルミ州の町)、砂糖、乾物などの売買が盛んに行われた。住民の大多数は野菜栽培、畜産に従事していた。この地で大成功をおさめた実業家ブーチンの名は有名である。ネルチンスクの「ブーチン家」に関しては、愛知県立大学「おろしゃ会」のホームページに掲載されているガルキン氏の「ブーチン物語」に詳しく紹介されている。
現在の町の様子
町の周囲は牧草地が多く、農牧主体の経済のようだった。ハム、ソーセージ類の食肉コンビナートがあるそうで、そこで出来たばかりハムをご馳走になったが、食肉コンビナートを訪問する時間は無かった。
名所旧跡など
・郷土史博物館(モーリタニア様式のブーチン家の建物(1860年))
1886年、この地方の大実業家だったブーチン家の邸宅(通称ブーチン宮殿)を利用して、クズネツォフにより開設された。仏教芸術、中国のブロンズ品のコレクション、その他の展示品がある。
・ヴォスクレセンスキー聖堂(1825年)
・交易所の建物
最近100年間のネルチンスクの人口推移
1897年: 6700人
1926年: 6500人
1939年:17500人
1959年:13500人
1970年:13400人
1979年:16900人
1989年:16900人
1992年:17000人
1996年:15300人
1998年:15200人
2000年:15100人
2001年:14800人
|
ネルチンスクにて
我々は予定到着時刻をだいぶオーバーしてネルチンスクへ到着した。到着したのはチタを出てから6時間後の夕方9時頃だった。もう外は暗くなっていたが、ネルチンスクでは市長のプロタソフさん、地区教育長のサハロフさんが出迎えてくれた。とりあえずレストランへ向かい、そこで遅い夕食となった。(しかし、この夕食がまだ今夜の夕食の前半となる事が後になってわかった。)夕食後、ホテルという所へ向かった。僕らが泊まったのは普通の三部屋のアパートをホテルにしたものだった。この事からも、この町への一般旅行者の来訪は希であるように思われた。
もうだいぶ遅い時間になっていたがサウナへ招待された。ロシア式サウナは湿式であり、熱した釜や石に湯をふりかけて、立ち上がる高温の生蒸気を室内に充満させる方法である。短時間に汗が滝のように流れ、それからうつ伏せに寝かされて、乾燥済みの白樺の葉を束ねたもので体全体をたたかれる。白樺の葉が揺れる度に室内の高温蒸気の流れが感じられ、熱さで息も絶え絶えになってくる。体内の不純物が汗とともに一気に排出され、血行も良くなるそうだ。
このサウナは小中学生が夏休みに長期間交代で過ごすキャンプ場(昔は「ピオネールのキャンプ場」と言っていた)の守衛小屋に付属していた。その関係もあったのか、サウナを出たらキャンプ場の食堂に招待され、二回目の夕食となってしまった。子供達が歌や踊りで歓迎する手はずだったそうだが、ホテルからサウナへ向かったのが夜の十時過ぎ、サウナを出て、食堂へ向かったのがもう真夜中になっており、子供達はすでに引き上げていた。しかし、広い食堂には料理やウオッカが並んでいた。すでに満腹状態ではあったが、大歓迎を受けてしまい、もう一度気合いを入れて二回目の夕食にチャレンジした。
|

ホテルの窓から
この時期、昼は30度を超える高温になるが、大陸性気候のシベリアでは朝方の気温は下がり、
窓を開けると澄んだ空気が心地よい風となって室内に入る。
窓からながめた町の風景は実にのどかだった。
ダーチャ(菜園別荘)にあるような木造平屋の人家が並んでいた。
僕がこの町へ来たのは初めてであるが、この風景はだいぶ昔にどこかで見たような感じがした。
よく見ると、それぞれの家には大きなパラボラアンテナが設置されており、
それが何十年も時計が止まってしまったような風景で、唯一「現在」を強調しているように思えた。
|

郷土史博物館
(旧ブーチン邸) |
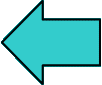 郷土史博物館は、1886年、この地方の大実業家だったブーチン家の邸宅を利用して、クズネツォフにより設立された。仏教芸術、中国のブロンズ品のコレクション、その他の展示品がある。 郷土史博物館は、1886年、この地方の大実業家だったブーチン家の邸宅を利用して、クズネツォフにより設立された。仏教芸術、中国のブロンズ品のコレクション、その他の展示品がある。 |
 |
中にはブーチン家の家族の写真や、当時ブーチン家が行っていた事業を紹介する写真なども展示されていた。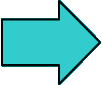
|

鏡の間
|
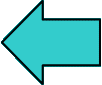 ここで最も印象深かったのは19世紀にフランスから運ばれたというヴェネツィアガラスの巨大な鏡だった。最初は海路太平洋を渡り、間宮海峡のアムール川河口まで運ばれ、そこからアムール川を艀で運ばれたそうだ。おそらく大きな荷馬車も必要だったであろう。鏡は4メートル四方程度だったが、当時としてはかなりのものだったに違いない。 ここで最も印象深かったのは19世紀にフランスから運ばれたというヴェネツィアガラスの巨大な鏡だった。最初は海路太平洋を渡り、間宮海峡のアムール川河口まで運ばれ、そこからアムール川を艀で運ばれたそうだ。おそらく大きな荷馬車も必要だったであろう。鏡は4メートル四方程度だったが、当時としてはかなりのものだったに違いない。
昔のブリヤート人の風俗を伝える写真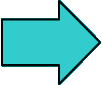
|

|

ベケトフの探検ルート |
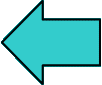 ネルチンスクをめざしたベケトフのルートは川沿いであった。バイカル湖からセレンガ川を溯り、その支流のヒロク川へ分け入り、しばらく進んで現在のチタ市の手前でヒロク川を離れ、インゴダ川へ移ったようである。インゴダ川は間もなくオノン川と合流し、シルカ川となる。そのシルカ川へ注ぐネルチャ川の河口付近に最初の小さな越冬用の砦が築かれた。ちなみに、このルートは現在のシベリア鉄道のルートにもなっている。地図をながめると、ベケトフが1642年にバイカル湖の北方をレナ川沿いにヤクーツクへ到達したルートも記載されていた。 ネルチンスクをめざしたベケトフのルートは川沿いであった。バイカル湖からセレンガ川を溯り、その支流のヒロク川へ分け入り、しばらく進んで現在のチタ市の手前でヒロク川を離れ、インゴダ川へ移ったようである。インゴダ川は間もなくオノン川と合流し、シルカ川となる。そのシルカ川へ注ぐネルチャ川の河口付近に最初の小さな越冬用の砦が築かれた。ちなみに、このルートは現在のシベリア鉄道のルートにもなっている。地図をながめると、ベケトフが1642年にバイカル湖の北方をレナ川沿いにヤクーツクへ到達したルートも記載されていた。
|
 |
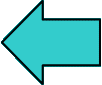 ネルチンスク砦の模型(ネルチンスク郷土史博物館) ネルチンスク砦の模型(ネルチンスク郷土史博物館)
ネルチャ川の中州に立ち入り、1658年に築かれたというネルチンスクの第二次砦跡へ向かったが、地上にその痕跡は無かった。数年前の発掘調査では砦の位置を証明するものが多数発見されたそうだ。当時の発掘調査に参加し、今回我々を案内してくれた博物館長のリトヴィンツェフさんと砦があったと思われる場所で記念撮影をした。(撮影・Samovar)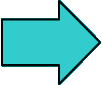
|
 |
 |
ヴォスクレセンスキー聖堂(1825年)
外観に大聖堂の面影は残っていたが、中は牛と馬があふれる家畜小屋と化していた。修復計画はあるそうで、既存の建物を残した部分改修か、全て撤去して全面改修するかは年内に結論が出される模様。 |
 |
 |
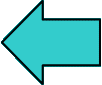 この地に最初のロシアの砦を築いたピョートル・ベケトフの記念碑 この地に最初のロシアの砦を築いたピョートル・ベケトフの記念碑 |
 |
ネルチンスク駅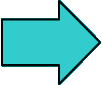
木造平屋の小さな駅だった。鉄道はここから7km離れたシベリア鉄道沿線駅のプリイースコヴィと接続されているが、近くで採掘されている鉱石の輸送用として利用されているようだった。
|

交易所跡 |
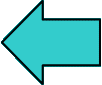 交易所だった建物 「1840年建設。全ロシア的意義のある記念碑は緊急な修復工事が必要とされており、修復計画の第一段階が完了した。」と壁に取り付けられたプレートに記載されていた。 交易所だった建物 「1840年建設。全ロシア的意義のある記念碑は緊急な修復工事が必要とされており、修復計画の第一段階が完了した。」と壁に取り付けられたプレートに記載されていた。 |

中国人事務所 |
中国人ビジネスマンが常駐しているという建物。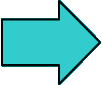
中国本土との連絡には衛星回線を利用しているのか、アンテナの数が多かった。
|

子供芸術学校入り口 |
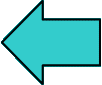 ネルチンスクは小さな町であるが、「子供芸術学校」があった。 ネルチンスクは小さな町であるが、「子供芸術学校」があった。
この地で子供達の情操教育に情熱を燃やしているナージャ先生。 |

先生の指導画 |
現代感覚のアニメテックな作品が多かった。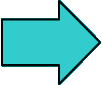
|

大昔に彫られたチベット文字
|
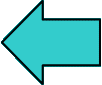 ウルグチャンというサナトリウムを訪問し、そこで有名だというミネラルウォータを飲んだ際に、「近場の岩山に意味不明の文字があり、それを読んで欲しい。中国人はわからなかったので、モンゴル語か日本語ではないか?」という要請があった。サナトリウムの所長が案内してくれたが、行ってみると、それはチベット語であり、僕らにもわからなかった。 ウルグチャンというサナトリウムを訪問し、そこで有名だというミネラルウォータを飲んだ際に、「近場の岩山に意味不明の文字があり、それを読んで欲しい。中国人はわからなかったので、モンゴル語か日本語ではないか?」という要請があった。サナトリウムの所長が案内してくれたが、行ってみると、それはチベット語であり、僕らにもわからなかった。 |

ネルチャ川 |
ネルチンスクを流れるネルチャ川。ネルチャ川はシルカ川の支流であり、シルカ川は、その先でアルグン川と合流し、アムール川となる。アムール川の支流の、さらにまた支流であるが、川幅は広い。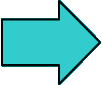
|
 |
市長さん、地区教育長さんのはからいで、ネルチャ川のほとりで憩いの時を過ごした。ハバロ教育大のコピチコ先生や、ザバイカル教育大のワシーリエフ先生は川の中で泳ぎ、喚声を上げていた。
羊のスープは脂濃かった。
|
 |

シャシリクはアウトドアの代表的な料理 |
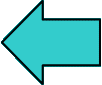 次々料理が運ばれた。教育長の仲間で、川の密漁監視員のクトゥーゾフさんはシャシリク(金串焼き肉)料理の専門家だった。 次々料理が運ばれた。教育長の仲間で、川の密漁監視員のクトゥーゾフさんはシャシリク(金串焼き肉)料理の専門家だった。 |

ガンチムールの丘
|
ネルチンスクを離れる時は市長さん、地区教育長さん、博物館長さんがガンチムールの丘まで見送ってくれた。そこは陽の当たるお花畑で、時間があったらもっと留まっていたい風景であった。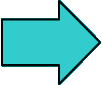 |
 |
 |
 |




























